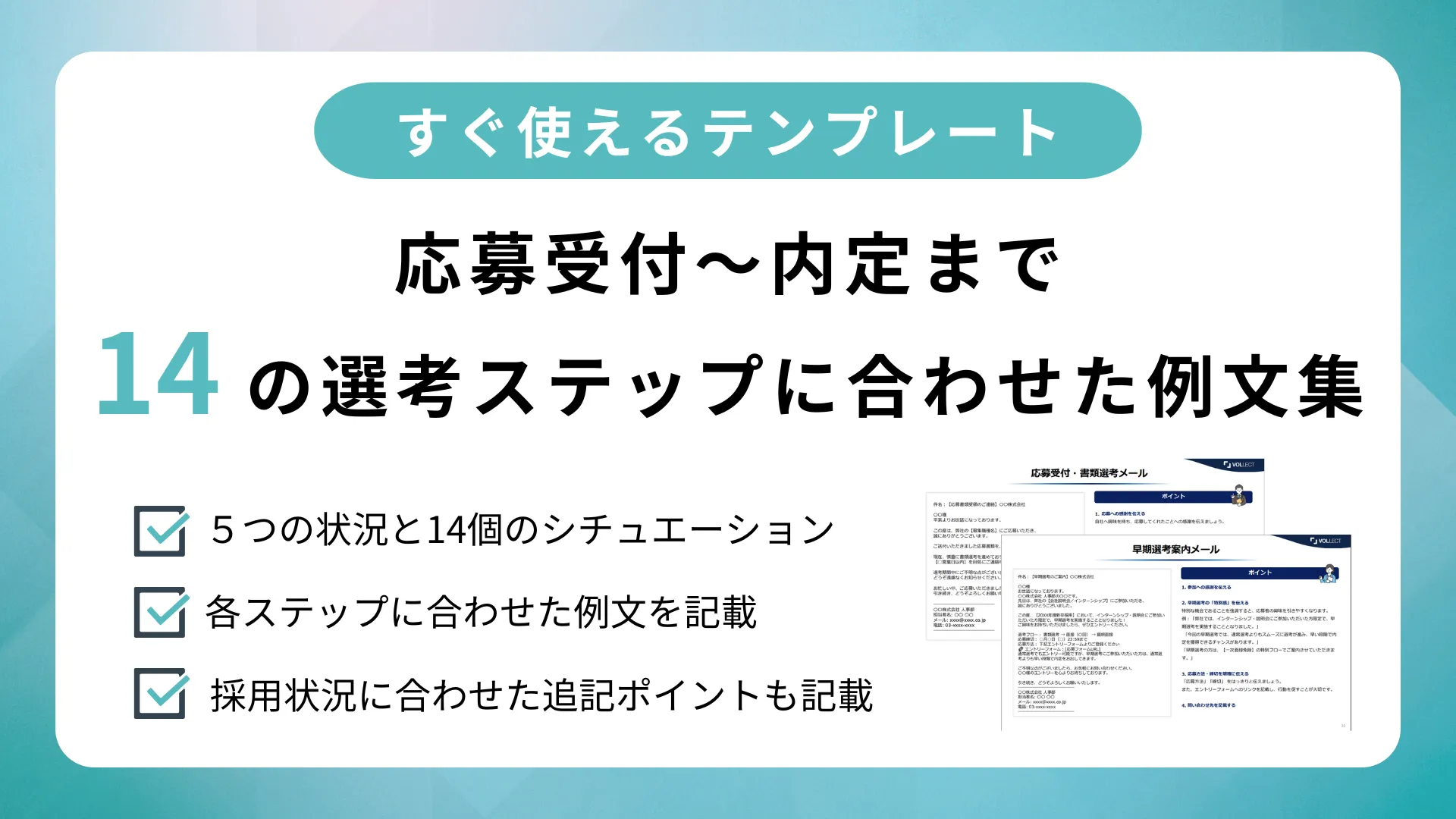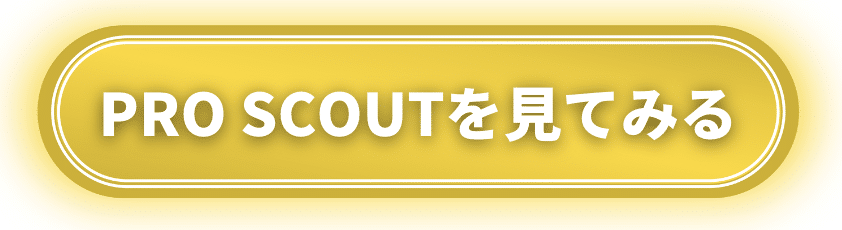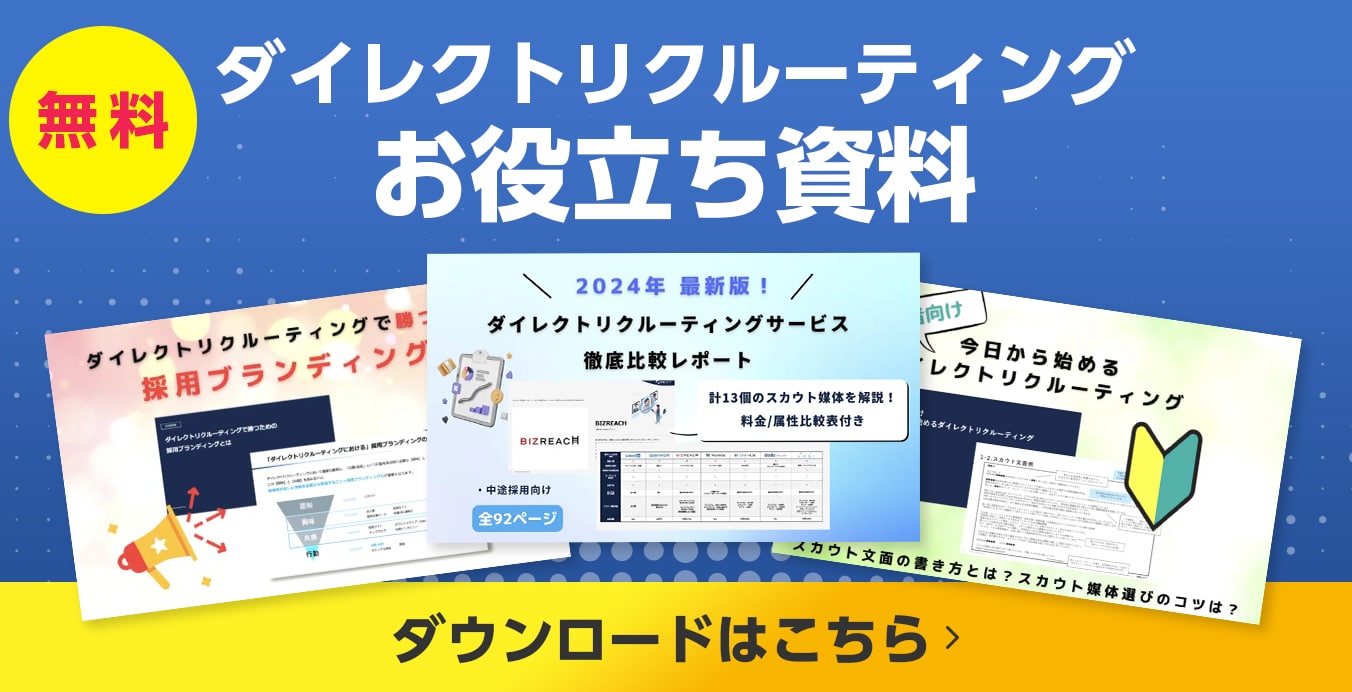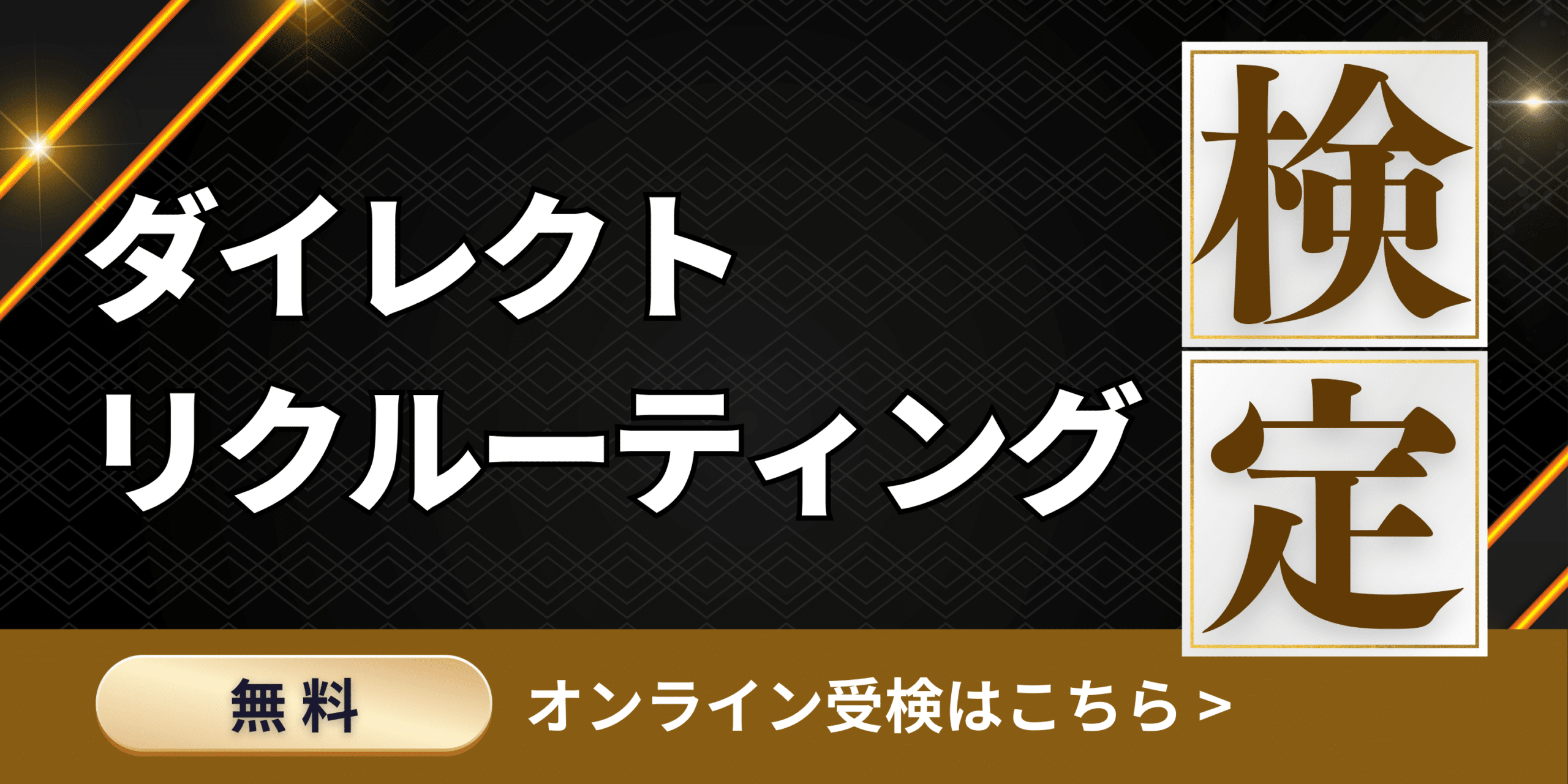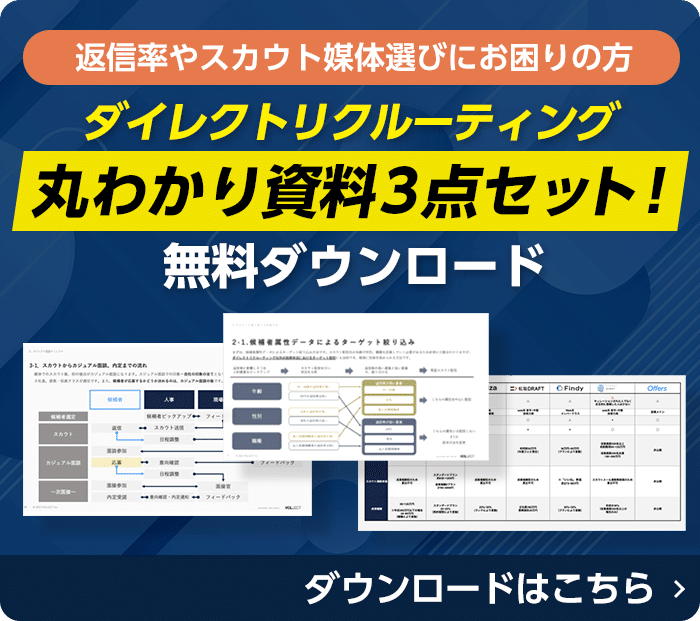企業側から面接の実施をお断りする際の伝え方と注意点
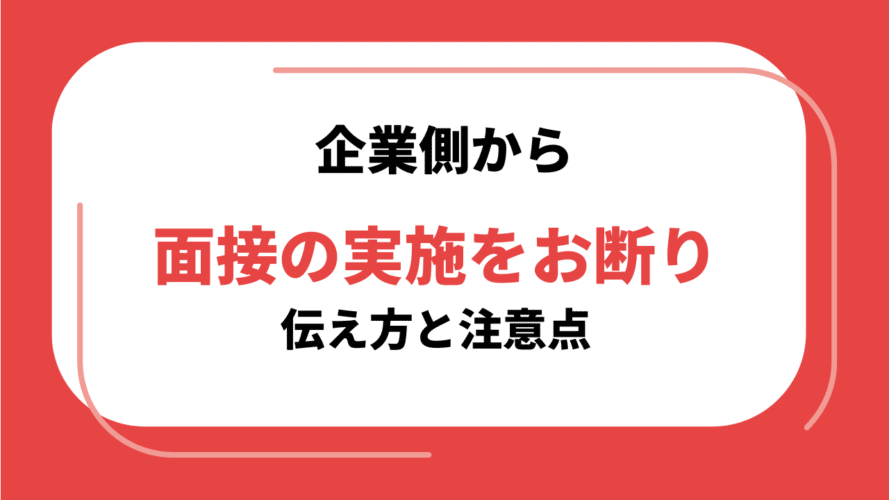
すべての応募者の面接を実施するのは難しいものです。
書類選考を経て、残念ながら面接に至らない場合には企業側から面接の実施をお断りする必要があります。
そこで今回は、企業側から面接の実施をお断りする際の伝え方と注意点を紹介します。
「面接実施をお断りする際は理由も伝えなければいけないの?」「どのような内容を伝えればいいの?」などとお悩みの採用担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
HRpediaでは、「採用メールテンプレートを見直したい...」「失礼のない、適切な表現で返信したい…」といった採用担当者のために、「応募受付から内定通知まで、即使える14種類のメール例文集」をご用意しております。
こちらからお受け取りいただき、スムーズな候補者対応にお役立てください。
目次
企業側から面接の実施をお断りする手段
企業側から面接の実施をお断りする手段は、3つあります。それぞれのメリットと注意点を解説していきます。
メールが最も一般的

メールでのお断り連絡は、最も一般的な方法です。近年では求人媒体にあるメッセージ・チャット機能を通じてやり取りすることも増えています。
連絡した履歴が残る、書面よりは早く伝えられるなどのメリットがあります。
メールやメッセージ・チャットでの通知の場合、他のメールなどに埋もれないよう、件名を一目見ただけで重要度と内容がわかるようにすることがポイントです。
例えば、「【〇〇〇〇株式会社】採用選考結果のご連絡」などとするとわかりやすいでしょう。
後述する電話や書面で伝える場合にも共通しますが、必ず応募への感謝の意を伝えることも注意すべきポイントの一つです。
現在の日本は労働人口の減少による採用難の時代であり、なかなか応募が集まらないのが現状です。そのような中で、数ある企業の中から自社を魅力に感じ、応募してくれたことに対し感謝の意を示さなければ、企業への印象は悪くなります。
企業への印象が悪くなると、SNSや口コミサイトで悪評を書き込まれる可能性があります。すると、応募人数が減ったり選考辞退や内定辞退が起こったりする可能性もあるのです。
どの連絡手段を採用するにせよ、感謝の意を伝えるなど、相手が不快にならず誠実な対応をすることが重要です。
スピード感があるのは電話
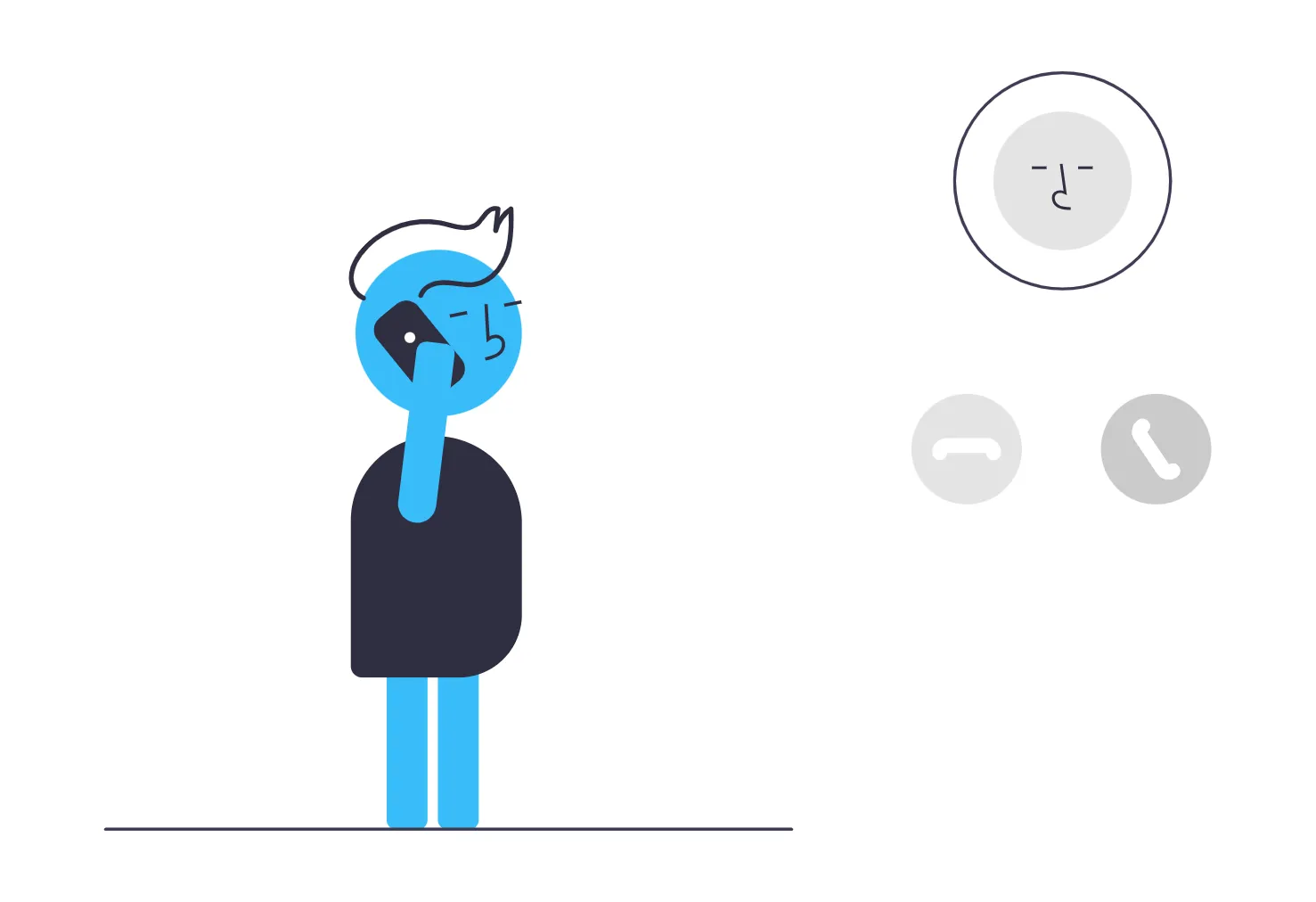
メールでの連絡が一般的ではあるものの、スピード感があるのは電話での連絡です。
電話であれば面接実施が困難だと判断した後に、すぐに連絡できます。また、直接コミュニケーションをとるため、真摯さが伝わるメリットもあります。
迅速に連絡できる手段ではあるものの、「早く伝えなければ」と思うあまりに早朝や深夜、土日祝日に連絡するのは避けるべきです。
また、留守番電話に繋がってしまった場合は、そこで面接お断りの旨を伝えるのではなく、改めて連絡し直接伝えるようにしましょう。
何度電話をしても出てもらえない場合はメールに切り替えるのも手段です。
HRpediaでは、「採用メールテンプレートを見直したい...」「失礼のない、適切な表現で返信したい…」といった採用担当者のために、「応募受付から内定通知まで、即使える14種類のメール例文集」をご用意しております。
こちらからお受け取りいただき、スムーズな候補者対応にお役立てください。
最近は少なくなったが書面も選択肢

近年では少なくなった書面での通知も、選択肢の一つです。履歴書や職務経歴書など、受領した書類を返却する場合などは同封しましょう。
注意点としては、他の応募者の書類を誤って同封しないようにすることです。個人情報の漏洩につながり、企業としての信頼度も低くなってしまうでしょう。
また、書面だとスピード感はなくなってしまい、手間もかかります。返却書類は後日送付とし、取り急ぎメールや電話などで結果を通知できないか検討してみましょう。
HRpediaでは、「採用メールテンプレートを見直したい...」「失礼のない、適切な表現で返信したい…」といった採用担当者のために、「応募受付から内定通知まで、即使える14種類のメール例文集」をご用意しております。
こちらからお受け取りいただき、スムーズな候補者対応にお役立てください。
面接の実施をお断りする場合の理由の伝え方
面接の実施をお断りする際、正直に理由を伝えなければいけないか悩む採用担当の方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?本章では、基本的な理由の伝え方と注意点を紹介します。
基本的な伝え方
基本的には、面接の実施をお断りする際の連絡で具体的な理由を伝える義務はありません。
面接の実施をお断りする際の通知は、形式的な記載で問題ないでしょう。
例:慎重に書類選考を進めさせていただいた結果、誠に恐縮ではございますが、今回は面接実施を見合わせる判断となりました。
理由を伝える場合の注意点
理由を伝える場合は、いくつか注意点があります。まず、理由を伝えることがトラブルに発展するリスクがあることを認識しましょう。受け取り手によっては、「差別された」「パーソナリティを否定された」と感じる可能性があるためです。
そのため、本当の理由を正直に伝えるのか、慎重に判断しましょう。
慎重に考慮したうえで伝えると判断した場合には、簡潔で納得感のある説明でなければいけません。また、応募者のパーソナリティーを低く評価する内容であってもいけません。
上記を考慮した内容を考え、複数人にチェックしてもらうなどして問題がない文章かどうか確認しましょう。また、次章で紹介する例文も参考にしてみてください。
HRpediaでは、「採用メールテンプレートを見直したい...」「失礼のない、適切な表現で返信したい…」といった採用担当者のために、「応募受付から内定通知まで、即使える14種類のメール例文集」をご用意しております。
こちらからお受け取りいただき、スムーズな候補者対応にお役立てください。
面接の実施をお断りする場合のメールの例文
本章では、面接の実施をお断りする場合のメール例文を紹介します。不採用理由別文章も3パターン紹介します。
また、先述したように不採用理由は必ずしも記載する必要はありません。【不採用理由により変更】の部分は削除して使用することも可能です。
自社や応募者に合った内容を選んでみてくださいね。
| 【件名】〇〇株式会社 採用選考結果のご連絡
〇〇 〇〇 様 平素より大変お世話になっております。 この度は、弊社の【募集職種】にご応募いただき、誠にありがとうございました。 慎重に書類選考を進めさせていただいた結果、誠に恐縮ではございますが、今回は面接実施を見合わせる判断となりました。 【不採用理由により変更】何卒ご理解いただけますと幸いです。 なお、応募いただきました貴重なご経験やスキルは、今後の参考とさせていただきたく存じます。 末筆ながら、〇〇様の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 敬具 〇〇株式会社 採用担当 〇〇 |
応募者多数の場合
応募者多数のため、より自社に適した人材を採用する旨を伝える文章です。実際に幅の広い応募条件や好待遇求人などは、採用難の時代でも応募が集まりやすい傾向にあります。そのような場合に使用できる文章です。
【例文】
この度はありがたいことに、多数のご応募をいただいております。そのため、当社の現状により適した候補者さまを採用させていただくこととなりました。
会社の方針や状況の変化
いざ採用活動を始めてみたは良いものの、応募が集まらず複数の人材を見極める段階に至っていない、急な組織体制の変更で募集していたポストがなくなったなどは起こり得る事象です。
そのような場合は、以下のような文章を使用すると良いでしょう。
【例文】
理由といたしましては、大変恐縮ではございますが、現在社内環境の変化に伴い採用計画の再検討を行うこととなったためでございます。誠に心苦しい限りですが、今回は採用を見送らせていただくこととなりました。
スキルや経験のミスマッチの場合
求人広告など「待ちの採用」の場合、「必須条件」として記載しているスキルを保有していないにも関わらず、応募がある場合があります。
自社の求めるスキルや経験を有していない場合は、下記のような文章を使用すると良いでしょう。
【例文】
応募者様のこれまでのご経歴を拝見させていただきましたところ、お持ちのご経験やスキルが今回当社が求める条件と一部異なるとの判断に至りました。誠に心苦しい限りですが、今回は採用を見送らせていただきたく存じます。
HRpediaでは、「採用メールテンプレートを見直したい...」「失礼のない、適切な表現で返信したい…」といった採用担当者のために、「応募受付から内定通知まで、即使える14種類のメール例文集」をご用意しております。
こちらからお受け取りいただき、スムーズな候補者対応にお役立てください。
企業側から面接の実施をお断りする際に留意すべき法的事項
企業側から面接の実施をお断りする際には、留意すべき法的事項がいくつかあります。それぞれ解説していきます。
差別と捉えられかねない不採用理由は禁止
差別と捉えられかねない不採用理由は注意が必要な事項です。
性別
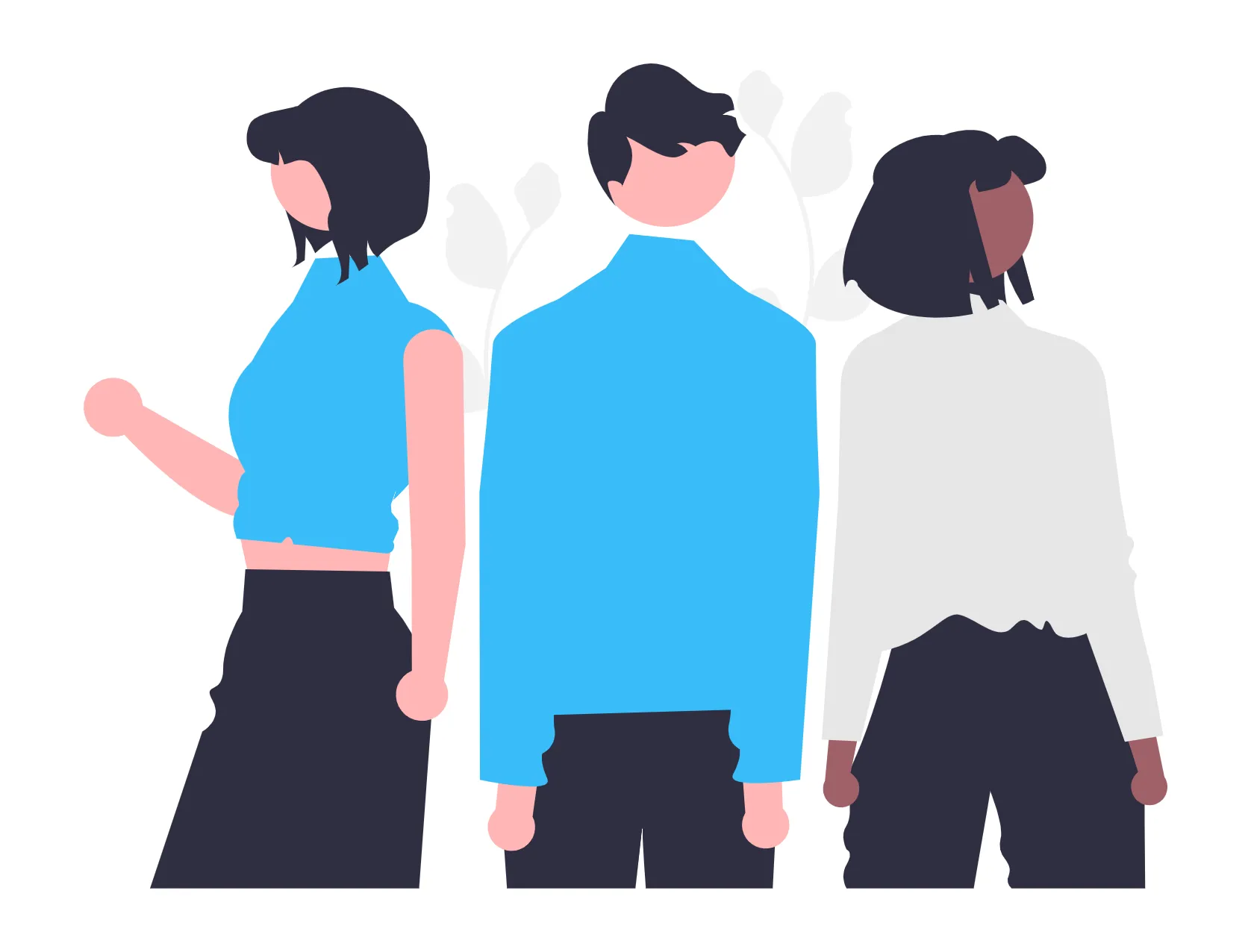
「男性だから」「女性だから」という風に、性別で不採用とすることは男女雇用機会均等法に抵触する可能性があります。
男女雇用機会均等法では、性別に関係なく均等な雇用機会を得られ、意欲と能力に応じた均等な待遇を受けられることを目的としています。
男女雇用機会均等法に違反すると、厚生労働大臣または都道府県労働局長から報告を求められたり、助言や指導、勧告を受けたりするのです。その勧告にも従わない場合、企業名が公表され、20万円以下の過料が課されます。
年齢
「若手ではないから採用しない」という不採用理由は、雇用対策法に抵触する可能性が高いです。年齢制限は原則禁止されているからです。
ただし例外的に、年齢制限が認められる場合もあります。こちらでは詳細は省きますが、下記の場合、例外的に年齢制限が認められます。
雇用対策法施行規則第1条の3第1項
- 例外事由1号:定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 例外事由2号:労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
- 例外事由3号イ:長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 例外事由3号ロ:技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 例外事由3号ハ:芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
- 例外事由3号ニ:60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
ただし、これは募集時に明記していないと適用されません。
詳しくは、厚生労働省のマニュアルをご覧ください。
信仰宗教
日本国憲法第20条では、信教の自由が保障されています。応募者の信仰している宗教で採用可否を判断することは、憲法に反していることとなります。
信仰する宗教によって応募者の適性や能力は左右されないため、牧師の採用など特別な事情を除き、信仰宗教によって採用可否を判断することは差別に当たるのです。
支持政党
支持政党に関しても宗教と同じく、個人の自由が尊重されるべき事項です。支持政党によって候補者の適性や能力は変わりません。「この応募者は〇〇党を指示しているから採用できない」という理由は、差別に当たります。
国籍や人種、出身地
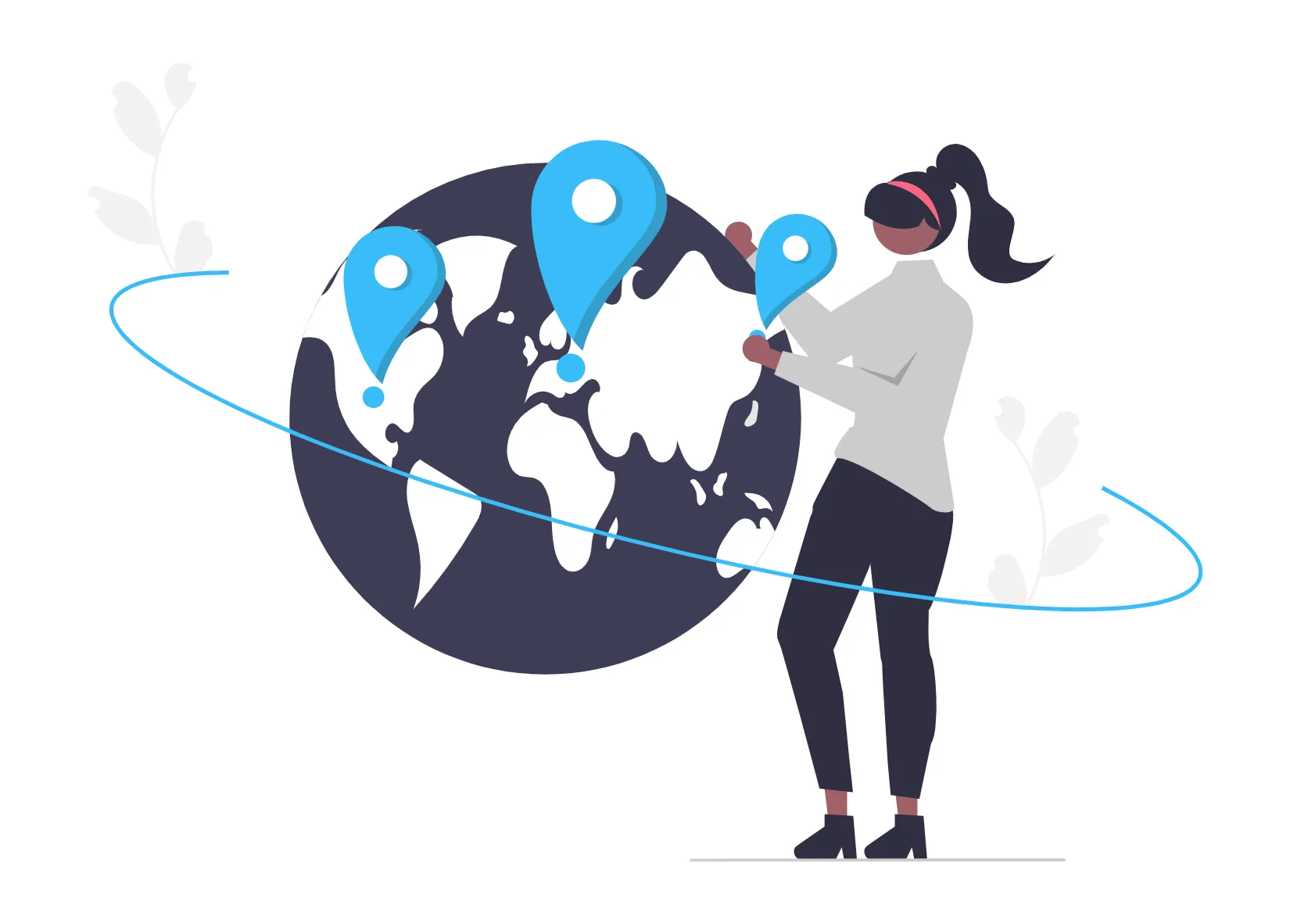
国籍や人種、出身地を理由に不採用とするのも、「差別だ」と捉えかねられません。
国籍・人種については、特定の国籍や人種を理由に不採用にすることは職業安定法で禁じられています。国籍の確認は、多くの会社が提出を求める住民票記載事項証明や雇用保険等の手続き時に自然と行うこととなります。また、在留資格の確認の確認も必要です。しかし、これはあくまでも「採用後」かつ手続きに必要であるなどの明確な理由があります。
また、差別が発生しやすいのは国籍だけにとどまりません。日本には昔から「部落差別」と呼ばれる、出身や住んでいる地域による差別が存在します。
江戸時代から続くこの差別は、今でも完全には解消されていません。逆に、ネットの普及によって差別地区が特定され拡散されるなど、新たな問題も生じてきています。
「あなたは〇〇の出身なので不採用となりました」などとは決して伝えず、また実際にそれを判断基準としてはいけません。
エントリーシートなどに本籍地や帰省先を記入させることも、それを理由に採用されなかったのではないかと捉えられる可能性があります。そのため、出身地を聞くような欄は設けないようにしましょう。
企業には「採用の自由」が認められているが無制限ではない
企業には、「採用の自由」が担保されています。採用の自由とは、人を雇用する企業、つまり「使用者側」に、雇用契約を結ぶときに認められる契約の自由のことを指します。採用の自由の中には「調査の自由」があり、採用時の考慮要素となる事情については自由に調査できることとなっているのです。
しかし、どのような内容でも「採用の自由」が適用されるわけではありません。
前項にて紹介した性別や信仰宗教のほかにも、業務内容と関係がないと判断される不採用理由は違反となる場合があります。
健康状態や病歴

健康状態や病歴を理由に不採用とする場合は、細心の注意を払う必要があります。
HIVやB型肝炎、C型肝炎などは職場で感染するリスクは非常に少ないです。また、色覚異常などの遺伝性障害については、就業上特別に配慮すべき事項がある場合のみの判断基準とするようにしましょう。感染リスクがほぼないにも関わらず、それを理由に不採用とすることは公正な採用選考を行っているとは言えず、訴えられるリスクがあるのです。
また、近年のストレス社会で精神疾患者が増加している関係で、候補者が精神疾患を患っていないか気になる企業も多いのではないでしょうか?応募者の精神疾患について調査することは、基本的に行ってはいけません。
ただし、「候補者に疾患がある場合、業務に甚大な影響を及ぼす恐れがある」と考えられる業種は、調査や質問をすることが許されます。ここで言う「甚大な影響」とは、業務を行うにあたり他者の生命に関わったり社会全体を脅かしたりすることを指します。例えば、うつ病のバス運転士がいたとしましょう。業務中、突然希死念慮におそわれ、事故を起こす可能性があります。
このような調査を行う場合、非常にセンシティブかつ個人的な情報のため、かなり慎重に取り扱うべきであり、細心の注意を払う必要があります。
「応募者についてどこまで調査して良いか」を考える場合は、「仕事に関するもの」かどうかがポイントです。例えば応募者の履歴書に、1年間のブランクがあったとします。「この期間、体調を崩されていたのですか?」と聞くのはNGです。さらに、「この期間は何をしていたのですか?」などと聞くのも仕事と直結しているとは言い難いためグレーゾーンです。「この期間はお仕事は何をされていましたか?」と聞くのは仕事に関する質問の範疇なので、問題ないでしょう。
健康診断項目や病歴、精神疾患有無などは個人情報保護上の「要配慮個人情報」に該当します。そのため、取得の前には本人の同意が必要となります。(個人情報保護法20条2項)
同意したことを明確にしエビデンスとして残しておくためには、個々人に同意書を書いてもらうと良いでしょう。同意書を作成する際のポイントは、利用目的を明示すること、健康情報について任意の回答を求める形で同意を取得することです。
ルールを守り、取得が必要な健康情報には十分に配慮したうえで、調査を行いましょう。不安な場合は弁護士や社労士などに相談することをおすすめします。
前科や犯罪歴
前科や犯罪歴で採用可否を決めるのは、プライバシーの侵害や差別にあたる可能性が高いです。
ただし、業務に関わる場合は例外的に調査して良い場合があります。例えば、バスやタクシーの運転手などを採用する場合、免許停止処分を受けていれば業務に就かせることはできません。また、交通違反を複数回重ねている場合は、安全に業務を遂行できないと判断できます。このような場合は、免許停止処分を受けていないか、交通違反を繰り返していないかなどを調査することは重要です。
前科や犯罪歴を聞く場合は、あくまでも業務に関わる項目のみ調査するようにしましょう。
経済状況

経済状況や財産は、本人の努力ではどうしようもできない事項であり、候補者の適性や能力を測る材料にはなりません。これを理由に採用可否を判断することは、プライバシーの侵害にあたる恐れがあります。
また、先述した平等な教育や就職の機会を与えられなかった部落差別による排除にもつながる恐れがあります。
思想や信条
思想や信条は、宗教などと同じように、本来個人の自由が尊重されるべき事項で、配慮すべきです。
思想の自由は日本国憲法第19条で保障されています。そのため、採用選考に持ち込むと基本的人権を侵害する可能性があるのです。
例えば、過去「三菱樹脂事件」と呼ばれる事件がありました。これは、学生運動に参加していた事実が発覚した内定者が本採用を拒否された事件で、裁判により和解が成立しました。
このように、思想や信条を理由に採用可否を判断するのは大きなリスクです。
応募書類の適切な処理が求められる
応募書類の適切な処理も、企業側から面接の実施をお断りする際に留意すべき事項です。
書類の返却義務はありませんが、企業には個人情報保護法の観点から適切な処理が求められます。
応募書類や選考記録をデジタル化して安全に保管し、保管期限を設定して適切なタイミングで破棄するなどの管理が必要です。また、アクセス権限を限定するなど、情報セキュリティにも十分な配慮が必要です。
社内で個人情報の記載がある書類やデータの保存方法について、マニュアルを作成しておくと便利でしょう。
個人情報保護は、今や企業が守るべき当たり前の事項です。個人情報を漏洩させてしまうと、応募者だけでなく、企業を取り巻くステークホルダーからの信頼が下がってしまいます。
面接お断りメールでお悩みならVOLLECTまで!
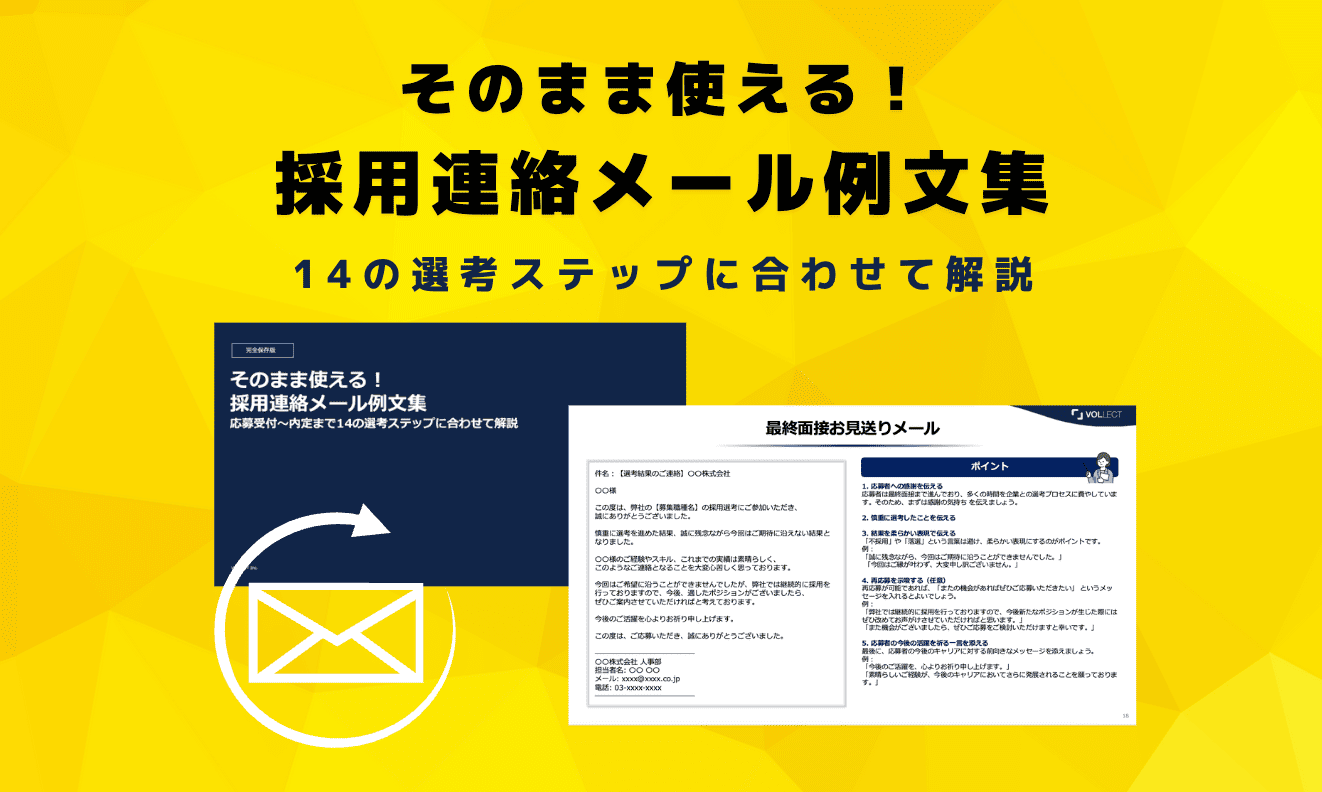
VOLLECTでは現在、「そのまま使える!採用連絡メール例文集」を配布しております。
面接お断りメールだけでなく、他の採用連絡に関する例文もありますので、お困りの採用担当者さまはぜひこちらからダウンロードください。
また、VOLLECTではダイレクトリクルーティングのご支援を中心とした「PRO SCOUT」もご提供しております。
戦略策定、KGI/KPI設定、スカウト文面・求人作成、スカウト配信、カジュアル面談、数値レポーティング、レクチャーまですべてお任せいただけます。
個社ごとにマッチした人材の採用代行をご提供いたしますので、採用でお困りの企業さまはぜひお問い合わせください。
まとめ
今回は、企業側から面接の実施をお断りする際の伝え方と注意点を紹介しました。
面接の実施をお断りする際は、必ずしも理由を伝える必要はありません。もし理由を伝える場合は、細心の注意が必要です。
企業には「採用の自由」があるものの、どのような理由でも適用されるわけではありません。業務内容と関係がないと判断される不採用理由は違反となる場合があります。
相手に不快感や差別されているという感情を抱かせず、真摯な連絡を心がけるようにしましょう。
投稿者プロフィール

- 株式会社VOLLECTにて採用コンサルタントとして従事。大手広告代理店のDXコンサルタント職や、大手IT企業でのエンジニア採用など、多数の採用支援実績を持つ。
最新の投稿
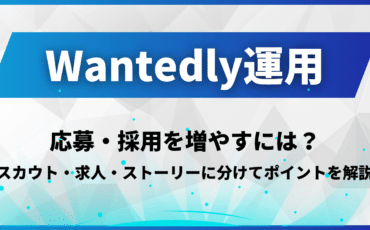
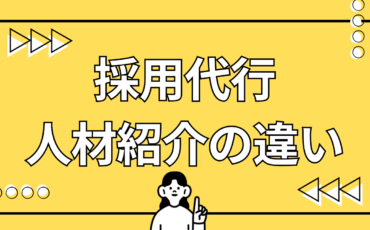
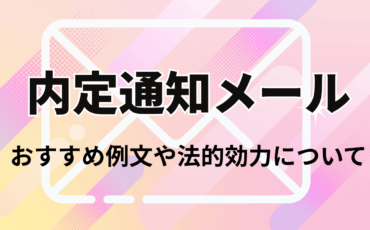
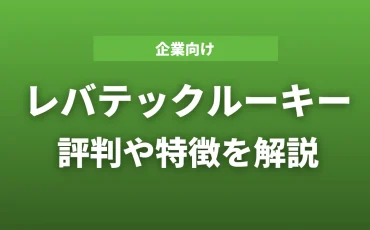 新卒採用スカウト媒体2025.03.31【企業向け】レバテックルーキーの評判や特徴を解説
新卒採用スカウト媒体2025.03.31【企業向け】レバテックルーキーの評判や特徴を解説