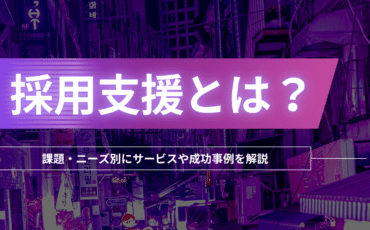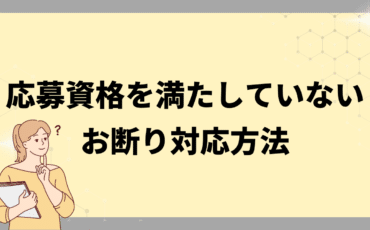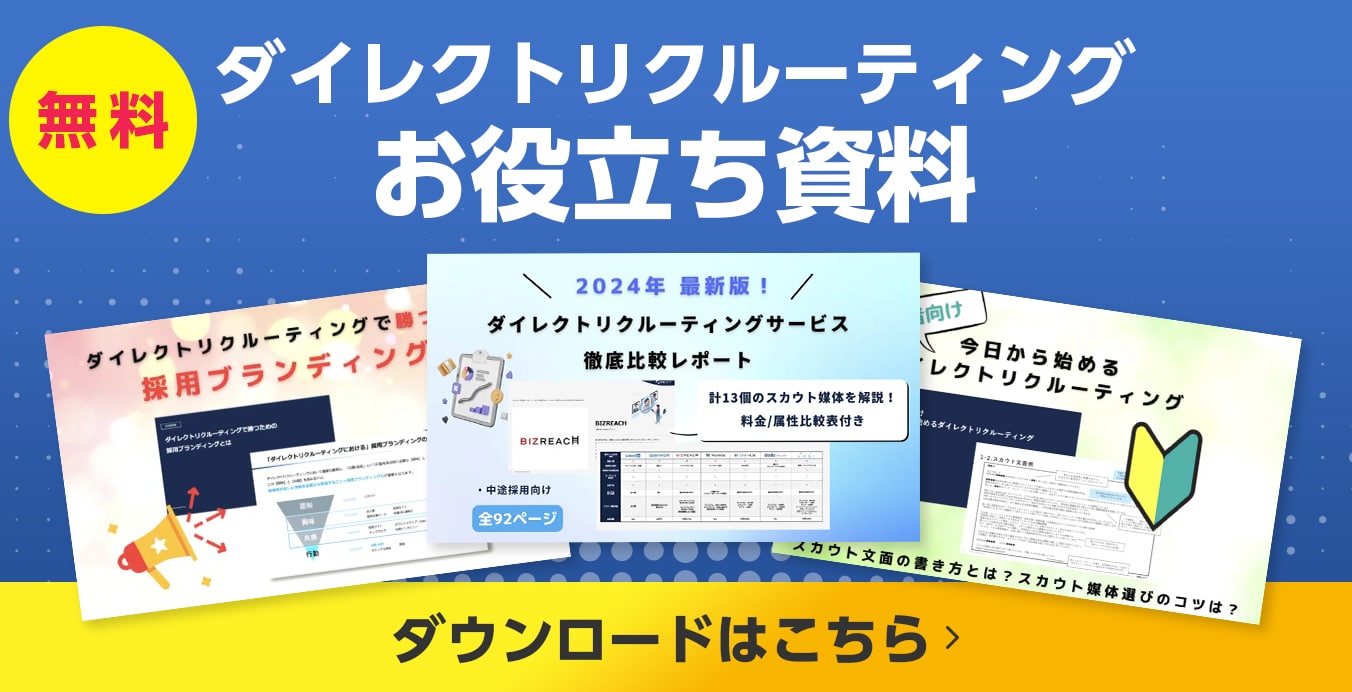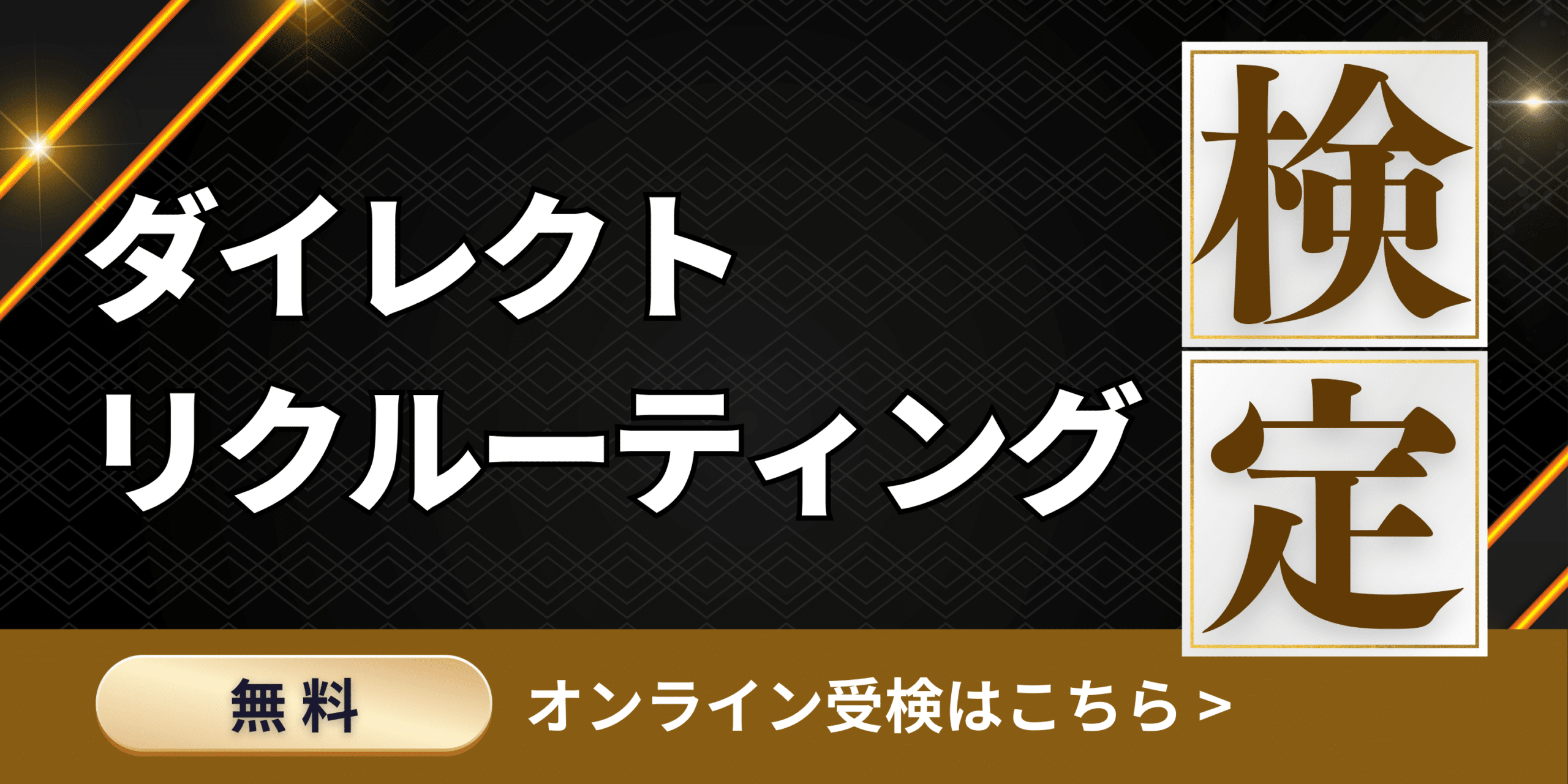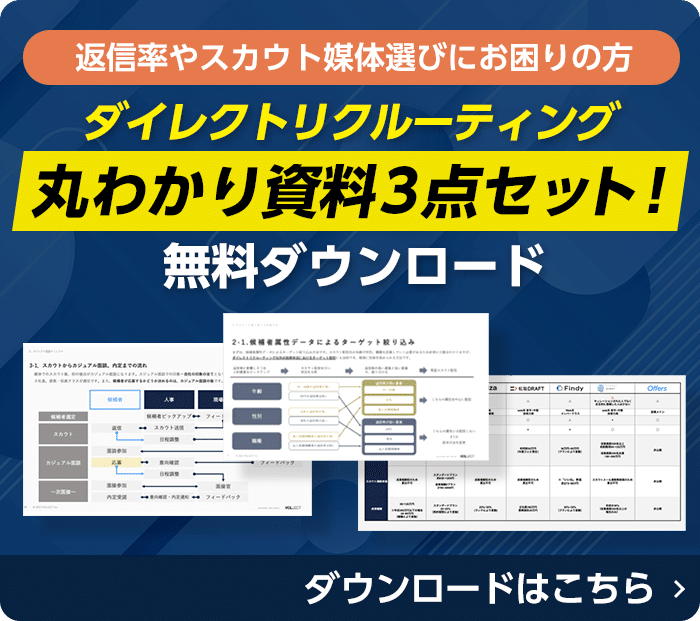【例文あり】応募したくなる文章とは?求人票の書き方を詳しく解説!
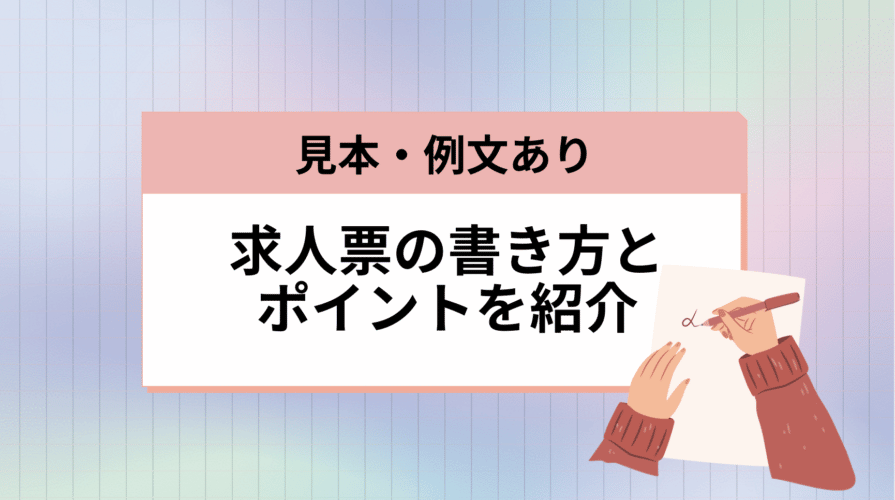
誰もが名前を知っているような有名企業でない限り、求人票に掲載されている文章が応募者の数を左右するといっても過言ではありません。
とはいっても、「どうすれば候補者の心を打つ文章を書けるのか分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、例文を交えながら応募したくなる文章(求人票)の書き方を詳しく解説します。
あわせて求人票に掲載してはいけない内容などについても触れるので、求人票の書き方でお悩みの企業の人事・採用担当者の方は、ぜひ参考になさってください。
「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。
こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!
800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」
スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。
サービス内容や料金を見る目次
応募したくなる文章(求人票)の条件
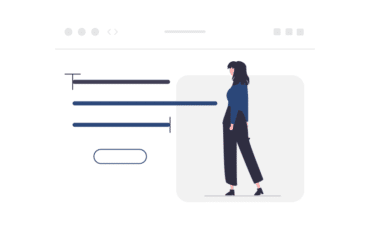
より多くの求職者から応募を獲得するためのポイントを紹介します。
検索されやすいワードを散りばめられている
求職者はインターネット上で求人票を検索します。必要最低限の項目を記載するのではなく、求職者が良く検索するようなキーワードを散りばめ、なるべく多く求職者の目に留まるような求人票を作成しましょう。
リモートワークやフレックス制度は、最近重要視する候補者が増えているので、記載すべきです。
内定までの流れが分かりやすく記載されている
応募してから内定まで、どのようなステップがあるのかを記載しましょう。WEBテストの有無や面接の回数、また面接はオンラインなのか会社で実施するのかなども記載しましょう。
例)応募→書類選考→WEB面接(2-3回)→最終面接(本社にて)→内定
残業時間も正直に記載されている
働き方を想像してもらうためにも、残業時間についてはわかりやすく記載しましょう。
毎日平均して何時間残業が発生しているか、繁忙期に何時間程度残業が発生するのか等、具体的な数値を用いて記載しましょう。また、裁量労働制を導入している場合でも求職者は残業時間について気になる人がいるため、求人票を見ただけで不明点を解消してもらえるよう具体的な数値を記載するのがお勧めです。
「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。
こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!
800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」
スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。
サービス内容や料金を見る求める人物像が明確
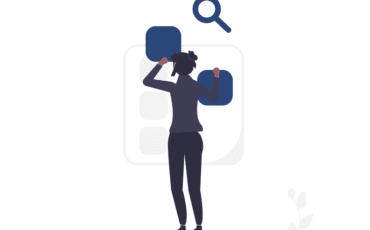
若手を対象としているのか、ベテラン層(プロフェッショナル)を対象としているのか、わかりやすく記載しましょう。前述の通り、年齢に関する記載はNGですが求めるスキル・経験の欄に具体的に記載するのがお勧めです。
例)若手を採用したい場合
第二新卒募集
未経験者には、研修制度あり
例)ベテラン層(プロフェッショナル)を採用したい場合
XXの領域で10年以上実務経験のある方
5名以上のマネジメント経験5年以上
専門用語を使わずにわかりやすい言葉で書かれている
求職者の応募までの心理的ハードルを引き下げるため、専門用語を避けましょう。難しそうに見える求人票よりも、面白そう・自分に務まりそうと思ってもらえるような求人票にして、なるべく多くの求職者から応募がもらえるようにしましょう。
求人票はできるだけ詳しく、具体的に記載することが大切です。特にこの求人票を見る人が、業界の未経験であれば、未経験の人でもわかるように出来るだけ噛み砕いて説明しましょう。
例)
■お任せしたいお仕事内容について:
企業の採用担当者に対してダイレクトリクルーティングを中心とした採用コンサルティングをお任せ致します。
※ダイレクトリクルーティングとは、企業の人事/採用担当者などが「直接」転職希望者や転職潜在層に対してアプローチを行うPUSH型の採用手法のことです。これまでの転職市場では、求人メディアに広告を出し応募を待つ、人材エージェントを利用して紹介を待つ、つまり何か(誰か)を間に挟んで「待つ(=PULL型)」採用でした。それに対してダイレクトリクルーティングでは、企業の採用担当者が自ら、BIZREACH等に代表される候補者データベースにアクセスし、自社の採用要件にマッチした候補者をデータベースから探し出して、スカウトメールを送るなどのアプローチを行います。
採用したいターゲットにとって響く内容になっている
求人の魅力は誰にでも響く魅力ではなく、採用したいターゲットにとって響くのかを考えて選ぶ必要があります。
例えば30代女性をターゲットにしているのであれば、「何をポイントに転職をするのか?」を考えて、打ち出す魅力を考えましょう。
30代女性の例)
リモート&フレックス勤務OK♪それぞれが力を出せる場所で働ける!
創業4年目にして前年比150%成長中☆
オフィス備品や能力開発費補助等、仕事に専念できる福利厚生が充実♪
≪リモート/フレックス/渋谷駅直結≫
写真が効果的に使われている

魅力的な求人票にし、求職者の応募意欲を高めるためにオフィスの様子や従業員の様子等を掲載することも効果的です。写真は必ずしもプロが撮影したものでなくても構いません。
求人票に写真を掲載する欄がない場合は、自社WEBサイト等にオフィスの様子を掲載しましょう。
組織構成について記載されている
求職者に働く環境をイメージしてもらうために、組織構成を記載しましょう。
社長や部長の傘下にどのようなチームがあるのか、組織内で昇進したり、キャリアパスをどのように広げることができるのかなどを想像してもらうことができます。また一緒に働くチームメンバーの中で、業務がどのように分担されているのかを記載するのも効果的です。
「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。
こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!
800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」
スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。
サービス内容や料金を見る応募したくなる文章(求人票)の書き方
求人票を作成する際の具体的な書き方について説明します。
タイトル
タイトル(職種名)は求職者が一番初めに目にする項目です。タイトルから仕事内容が簡単にイメージできるように、わかりやすいタイトルを作成するように心がけましょう。
営業職 → 広告の企画営業職//土日祝休み/飛び込み・新規営業一切なし!
経理職 → 事業拡大を支える経理メンバーを募集 / リーダー候補
仕事内容
仕事内容は求人票の核となる重要な部分です。具体的に、どのような仕事を行うのかが誰が見てもわかるような文章を作成しましょう。箇条書きで記載しても構いません。
また、研修がある場合は研修内容や、「残業なし」といった働き方に関するキーワードを入れたり、1日のスケジュール・業務の流れを記載するのも効果的です。
【セールス業務】
①資料請求やお問い合わせへの対応 :Web上でリード獲得の仕組みを構築しているため、新規のテレアポ業務などはありません。問い合わせに対して情報提供などを行い、具体的なニーズにつなげていきます。最終的には契約書の締結などまで行います。
②お客様との商談 :人材要件のヒアリングや顧客の課題のヒアリングを行い、それに対して同社でどう役に立てるかを思考し提案を行って頂きます。希望人材に合う推奨利用メディアの選定、プロセスの見直し、スカウト文の練り直し等を行います。
求めるスキル・経験
どのような人を採用しているのか、禁止項目を避けながら記載しましょう。必須条件(その業務を行う上で必ず持っていないといけない資格や経験)と歓迎条件(必須ではないが、あると望ましい資格や経験)に分けて記載しましょう。
求職者が応募するかしないかを決める際の指標となるため、厳しすぎず、緩すぎない必須条件・歓迎条件を記載しましょう。
必須スキルは、必ず定量的に判断できる(誰が見ても同じ認識になる)ことが重要です。
例えば、「チャレンジ精神がある方」というのは、必須スキルには絶対に記載せず、求める人物像に入れるべきです。
複数個記載する場合は、必ず「下記いずれか」「下記いずれも」「下記2つ満たすのであれば」などの記載を加えましょう。
【必須経験の例】
・資金調達の経験
・5名以上の組織をマネジメントした経験
・医薬品業界での営業経験3年以上
・Java・C++言語でのシステム企画・構築・開発等の経験
【歓迎経験の例】
・製造業に関する業務知識
・IPO業務にかかわった経験
・個人向けの高額商品を扱った経験
・300人以上の組織での人事経験
募集背景
なぜそのポジションを募集しているのか、前向きな内容で記載しましょう。また、そのポジションに就いたら、どのようなキャリアパスが待っているのか想像できるような文言を加えましょう。
会社の特徴・理念・ビジョン
求人票のフォーマットによっては、企業紹介欄がないこともあります。その際は、ホームページなどに会社の特徴・理念・ビジョンをわかりやすく整理して置きましょう。
求人票に記載スペースがある場合は、求職者が応募したいと思えるようなその企業ならではの取り組みや、経営者の理念、今後のビジョンなどを記載しましょう。
報酬
記載は必須スキルの記載の次に、候補者が見るポイントです。報酬を記載する際は、月給制か年俸制を明記し、ボーナスの制度がある場合はどのような制度なのかも明記しましょう。また、求職者が初年度、3年後にどの程度の昇給が見込まれるかを記載すると、求職者に入社後の昇給幅をイメージしてもらうことができます。
また、「300〜1500万円」のような求人は、候補者にすると300万円の求人だと思われるので、最下限の年収の記載方法に注意しましょう。
年収の開きは、300万円程度が理想(500〜800万円)です。それ以上離れると、そもそもメンバーとマネジメントぐらい違うため、求人をメンバーポジションとマネジメントポジションで分けるべきです。
例)月給20万円 + 賞与年2回
30歳 営業リーダー:入社3年目、月給25万円
35歳 営業主任 :入社5年目、月給30万円
その他あると良い事項
- 年収の上がり幅
- 中途入社者比率
- 前職出身者
- 組織構成
- 社内におけるキャリアステップ
- 評価制度
求人票への掲載が禁止されている事項
求人票を作成する際、明記してはいけない禁止項目がいくつかあります。
性別を制限する表現
男女雇用機会均等法により、男女の違いを理由に待遇を分けたり、いずれかの性のみを採用することは禁止されています。また、職業名の記載方法でも注意が必要です。
避けるべきワード例
「看護婦さん」→「看護師」
「保母さん」→「保育士」
「セールスマン」→「営業社員」
「ガードマン」→「警備員」
年齢を制限する表現
雇用対策法により、年齢を制限した採用活動は禁止されています。 求人票を作成する際は、「30歳以上対象」や「20代採用中」といった表記は避けましょう。新卒を採用する際は、年齢ではなく「○○年3月大学卒業見込み」や「来春大学卒業予定者」といった表現を使いましょう。
詳しくは、厚生労働省の「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」をご覧ください。
出身地や国籍等を制限する表現
出身地・居住地を制限する表現は禁止されています。また、国籍や人種の記載も禁止されています。外国人を積極的に採用したい場合は「〇語がネイティブレベルの方を募集」「〇国での居住経験がある方を募集」といった表現に言い換えましょう。
「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。
こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!
800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」
スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。
サービス内容や料金を見る身体面を制限する表現
身長や外見、身体能力を制限する表現は禁止されています。力仕事が必要な求人の場合は、「体力がある方を採用」と記載するのではなく、仕事内容欄に「5kg程度の段ボールを運んでもらいます」といった内容を記載し、求職者自身に判断してもらうようにしましょう。
厚生労働省の定める求人票のルール
必ず守らなければならない、求人票の注意点を紹介します。
裁量労働制を採用する場合は「〇時間働いたものとみなす」と記載
2018年の職安法改定により、裁量労働制を採用している場合は、以下のような記載が必要です。
(例)「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」
そもそも、求人の前に、労使の協定・決議で適切に導入を決め、労働基準監督署に届け出る必要がありますので厚生労働省の「裁量労働制の求人を行う際の留意点」を参考にしましょう。
裁量労働制は、制度の対象業務のみに導入し適切に実施してください。
固定残業代を払う場合の明示事項が決まっている
2015年10月に施行された『若者雇用促進法』により、固定残業代、みなし残業代、見込み残業代、定額残業代を支払う求人に関しては、下記の3点全てを求人広告の給与欄などに明記することが義務付けられています。
該当する求人につきましては、下記3点の内容をご記載ください。参照:厚生労働省
(1)固定残業代(みなし残業代)に該当する金額
(2)固定残業として設定されている時間
(3)それを超えた際は割増賃金を追加で支払う旨
正確かつ最新の内容に保つ義務がある
以下の措置を講じるなど、 求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
- 募集を終了 内容変更したら、 速やかに求人情報の提供を終了 内容を変更する。
例: 自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する。 - 求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映する
よう速やかに依頼する。いつの時点の求人情報か明らかにする。例: 募集を開始した時点、 内容を変更した時点等
- 求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速や
かに対応する。
求人票とスカウト文面に掲載すべき情報の違い
スカウト文面は興味喚起をさせることが目的です。スカウト文面の情報量を増やしすぎると、スマートフォンでスクロールが多くなり離脱されやすいです。しかし、求人票は興味を持った候補者が見るものなので、できる限り詳しく、網羅的に記載することが求められます。
企業の魅力がたくさんあったとしても、スカウト文面はその中からワンメッセージに絞り込んで書くべきです。その代わり、募集要項には魅力を詰め込むと良いでしょう。
<スカウト文面に書くべき情報>
候補者のスキルや経験、希望にマッチしている旨
会社概要・簡潔な魅力
採用背景
その方に任せたい業務内容や役割
初回接触はカジュアル面談なのか・一次面接なのか
参考記事
<求人票に書くべき事柄>
会社概要・理念・ビジョン
仕事内容
求めるスキル・経験
募集背景
報酬・報酬例
年収の上がり幅
福利厚生
中途入社者比率
前職出身者
組織構成
社内におけるキャリアステップ
評価制度 等
虚偽の表示の禁止
① 業務内容
職種や業種について、 実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはなりません。下記はNG例です。
- 営業職中心の業務を 「事務職」 と表示する
- 契約社員の募集を 「試用期間中は契約社員」 など、 正社員の募集であるかのように表示する
- フリーランス (委託) の募集と雇用契約の募集を混同する
②募集者の氏名または名称
優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記載する等、 求人企業とグループ企業が混同されるような表示をしてはなりません。例えば、A社のグループ会社B社の求人を、 「A社は高度なITエンジニアのスキルを持った方を必要としています。」と表示するのはNGです。
また、社内で特に給与が高い労働者の給与を全ての労働者の給与であるかのように例示するのは禁止です。【給与】 400万円~ 【モデル給与】 1000万円~など、モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示するのはNGです。
求人票の書き方でお困りなら「PRO SCOUT」

「PRO SCOUT」では、600社以上の実績をもとにダイレクトリクルーティングを中心とした採用ご支援が可能です。
エンジニア採用案件には元エンジニアが担当するなど、各領域のプロフェッショナルが業界のトレンドを把握しながら他社事例をもとに採用をご支援します。月額10万円〜と料金もリーズナブル。
スカウトを送る時間が割けない、スカウトで採用決定を出したい、などのご希望がありましたら、ぜひ下記より詳細をご覧ください。
まとめ
応募たくなる求人票の文章の書き方についてお伝えしてきました。
求人票に記載する文章でよくありがちな失敗として、「企業が伝えたいことばかりを並べ立ててしまい、候補者に何も響かない」といったことがあります。
自社の都合ではなく候補者が求めている情報は何なのかにフォーカスし、その上で、自社が提供できるバリューを提示することで、応募したくなる求人票に近付くことができるでしょう。
この記事が、貴社の応募者数を増やすことにつながれば幸いです。
投稿者プロフィール
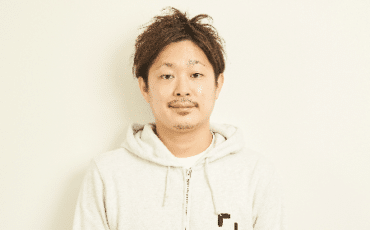
- 株式会社VOLLECT CEO
- 「ダイレクトリクルーティングの教科書」著者。日経トレンディや東洋経済への寄稿も果たす。新卒でパーソルキャリア株式会社にてクライアントに対して採用コンサルティングに従事。その後、外資系コンサル企業の採用支援をする中でダイレクトリクルーティングの魅力に気づき株式会社VOLLECTを創業。スカウト採用支援実績は800社超。
最新の投稿
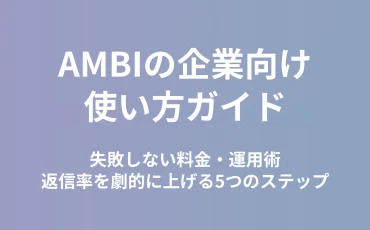 中途採用スカウト媒体2025.07.02AMBIの企業向け使い方ガイド|失敗しない料金・運用術と返信率を劇的に上げる5つのステップを解説
中途採用スカウト媒体2025.07.02AMBIの企業向け使い方ガイド|失敗しない料金・運用術と返信率を劇的に上げる5つのステップを解説 中途・新卒兼用スカウト媒体2025.07.01LinkedIn活用マニュアル 会社ページ作成からスカウト文例作成まで4ステップで解説
中途・新卒兼用スカウト媒体2025.07.01LinkedIn活用マニュアル 会社ページ作成からスカウト文例作成まで4ステップで解説